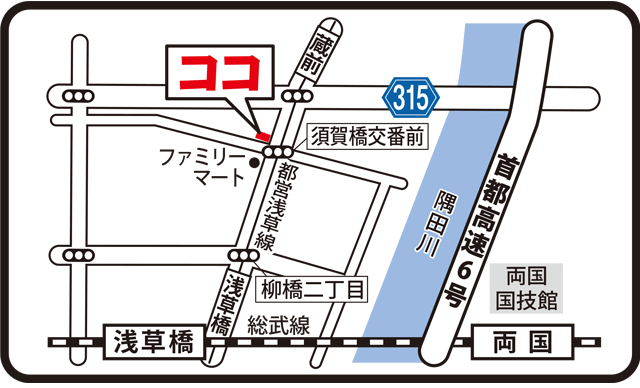こんにちは、浅草橋駅前鍼灸接骨院です。
いま周りで野球の話題が出る事が多くありましたので、今回は野球にまつわる痛みに関してお伝えいたします!
野球肘とは?
野球肘とは、野球の投球動作によって肘に過度な負担がかかることで起きる障害の総称です。特にピッチャーやキャッチャーなど、頻繁に強い投球を行う選手に多く見られます。
この障害は、大きく以下の3つのタイプに分けられます。
-
内側型(内側上顆炎):肘の内側の靭帯や骨が損傷します。成長期の選手に多く見られ、「骨端線障害」と呼ばれることもあります。
-
外側型(離断性骨軟骨炎):肘の外側の骨や軟骨が損傷します。これも成長期の選手に多く、放置すると関節ネズミ(遊離体)になることも。
-
後方型(尺骨鉤骨折など):投球のフィニッシュ時にかかる負荷で肘の後方に異常が生じるタイプです。
野球肘の主な原因
-
投げすぎ(オーバーユース)
-
不適切なフォーム
-
筋力不足(特に肩や体幹)
-
柔軟性の欠如
-
休養不足や疲労の蓄積
成長期の肘はまだ完全に固まっていないため、無理な投球が繰り返されると、骨や軟骨、靭帯にダメージが蓄積されていきます。
症状と見分け方
野球肘の初期症状には以下のようなものがあります。
-
投球時に肘が痛む
-
肘の曲げ伸ばしがしづらい
-
投げた後に違和感が残る
-
痛みで投球フォームが崩れる
初期の段階では痛みが軽く、放置されがちですが、無理を続けることで状態が悪化します。違和感がある場合はすぐに専門医の診察を受けましょう。
野球肘の予防法
野球肘は、正しい知識と日頃のケアで予防が可能です。以下のポイントに注意しましょう。
-
投球制限の遵守
1日に投げる球数や登板間隔を守ることは非常に重要です。特に成長期の選手には、1日の投球数を80球以内に抑えることが推奨されています。 -
正しい投球フォームの習得
フォームが崩れると、肘にかかる負担が増えます。コーチや専門家の指導を受けてフォームを改善しましょう。 -
体幹・下半身の強化
投球動作は腕だけでなく全身を使います。特に体幹と下半身の安定性が重要です。 -
柔軟性の維持
肩関節や股関節、ハムストリングスの柔軟性を保つことで、肘への負担を減らせます。 -
定期的なメディカルチェック
違和感がなくても、定期的に整形外科で肘の状態をチェックすることで、早期発見・早期対処が可能です。
主な治療法
野球肘の治療法には、症状の程度やタイプに応じて保存療法と手術療法の2つがあります。
まず多くのケースで選ばれるのが保存療法です。これは安静を基本とし、一定期間(2〜3ヶ月)投球を中止します。同時に、アイシングや消炎鎮痛剤の使用、肘周囲のストレッチや筋力トレーニングを行います。痛みが引いてから、理学療法士などの指導のもとで投球フォームの見直しやリハビリを進めていきます。
しかし、保存療法で改善が見られない場合や、骨や軟骨が損傷している場合には、手術が検討されます。代表的なのが、**内側側副靭帯再建術(トミー・ジョン手術)**や、関節鏡による遊離体の除去手術です。術後はリハビリを経て、競技復帰までに約6ヶ月〜1年を要することがあります。
治療において最も大切なのは、早期発見・早期治療です。肘に違和感がある時点で医療機関を受診し、悪化を防ぎましょう。
まとめ
野球肘は、野球に取り組むすべての選手が知っておくべき障害です。痛みが出てからでは遅いため、日頃のケアやフォームの見直しが何より大切です。
ケガを防ぎ、長く野球を楽しむためにも、野球肘に関する正しい知識を身につけておきましょう。
当院でも電気治療やストレッチなど症状に合わせた治療が出来ますのでお気軽にご連絡下さい!