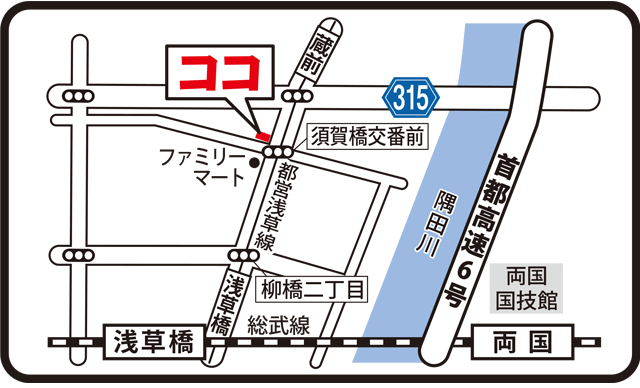皆さんこんにちは!
浅草橋駅前鍼灸接骨院です!
7月になり本格的に夏本番に近づいております。
ここ数年、気温が高くなっており夏バテに早い時期からなる方が多くいらっしゃいます。今日はその夏バテ防止法を鍼灸師観点からお知らせしたいと思います。

夏は高温多湿で体力を消耗しやすく、食欲不振やだるさ、寝苦しさによって体調を崩す人が増えます。これを一般的に「夏バテ」と呼びますが、東洋医学では夏バテを単なる疲れとは捉えず、「気(エネルギー)」と「水(体液)」のバランスの乱れとして考えます。
東洋医学では、夏は「心臓」、東洋医学では「心」と呼ばれますが、「心」の季節とされます。「心」は血液を全身に巡らせ、精神を安定させる役割を担っています。暑さで汗を多くかくと体内の「気」と「体液」が一緒に消耗され、心の働きが弱まり、倦怠感や不眠、動悸などの症状が現れやすくなります。
このような状態を防ぐためには、まず「気」を補い、「体液」を守ることが大切です。夏は冷たい物を摂りすぎて胃腸が冷えやすく、消化機能が落ちて気を十分に作れなくなります。よって、東洋医学では冷たい飲食を控えめにし、温かいお茶やスープで内臓を温めることを勧めます。特に胃腸を元気にする「健脾(けんぴ)」の考え方が重要です。
また、水分補給は大切ですが、一度に大量の冷水を飲むのではなく、常温や温かいお茶をこまめに摂る方が体に優しいとされます。麦茶やハトムギ茶は体内の熱を取り除きつつ利尿作用で余分な湿気を排出してくれるため、夏に適したお茶です。
食事面では、気を補う代表的な食材として、うなぎ、鶏肉、豆類、山芋、かぼちゃなどが挙げられます。これらは消化器官を強化し、気を生み出す助けになります。また、トマトやきゅうり、スイカなどの夏野菜は体内の余分な熱を冷まし、退役を補ってくれるので、適度に取り入れましょう。ただし、食べ過ぎると体を冷やしすぎるので注意が必要です。
さらに、冷房の使い過ぎも夏バテの原因になります。東洋医学では、冷たい風に長時間当たると「寒邪(かんじゃ)」というものが体に入り、気の流れが滞ると考えます。冷房は外気との温度差を大きくしすぎないように設定し、直接風が体に当たらない工夫をしましょう。
そして、夏は日の出が早く日没が遅いため、活動的になりやすい季節です。しかし夜更かしは「心」の負担を増やすため、東洋医学では夏こそ早寝早起きを心掛け、しっかりと睡眠をとることが養生の基本とされています。
最後に、軽い運動やストレッチで気の巡りを良くするのもおすすめです。汗をかきすぎない程度の朝の散歩やヨガ、深呼吸で心身を整え、夏の暑さに負けない体を作りましょう。
このように、東洋医学的な夏バテ対策は、体の内と外のバランスを整えることにあります。無理なく生活習慣を整え、夏を元気に乗り切りましょう。