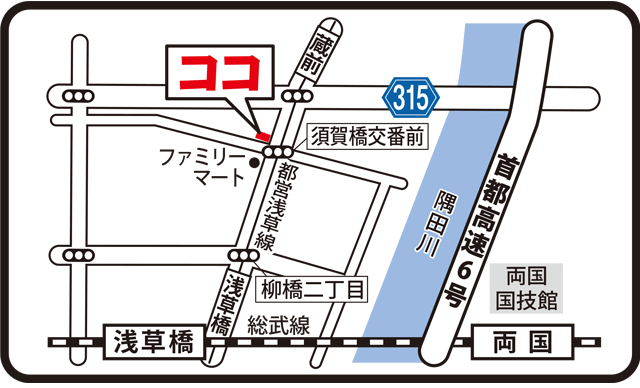皆さんこんにちは!
浅草橋駅前鍼灸接骨院です!
12月1週目が温かかった日がまるで嘘かのように冷え込んできましたね・・・
冷え込んでくると血管が収縮して体内の熱を逃がさないように働かせますが、血管が収縮すると血流が悪くなってしまい、血流障害を引き起こしてしまいます。
血流を良くする治療が沢山ありますがその中に鍼治療というものがあります。今回は鍼治療が血流にもたらす効果について説明します。
鍼治療は東洋医学の主要な治療法の一つで、経絡やツボを刺激することで体内のバランスを整え、健康を促進する目的があります。その中でも、血流に及ぼす効果は特に注目されています。
1. 血管の拡張と血流促進
鍼刺激は神経を介して血管を拡張させる作用があります。鍼がツボに刺入されると、その刺激が神経を通じて脳や脊髄に伝わり、血管をコントロールする自律神経が調整されます。この結果、血管が広がり血液の流れが改善されるとされています。この効果により、局所的な血流促進だけでなく、全身の循環が改善されることがあります。
2. 筋緊張の緩和
筋肉の緊張が強い状態では、血管が圧迫され、血流が妨げられることがあります。鍼は筋肉の緊張をほぐすことで血管への圧迫を減らし、血流をスムーズにする働きがあります。これにより、筋肉痛やこり、冷え性といった症状が改善されやすくなります。
3. 内因性の鎮痛物質と血流改善
鍼刺激によってエンドルフィンやセロトニンなどの鎮痛物質が分泌されることが研究で示されています。これらの物質は痛みを軽減するだけでなく、血管の拡張や血液の循環を良くする作用もあります。そのため、鍼治療は血流障害による痛みや炎症の改善にも役立つとされています。
4. 酸素供給と老廃物の除去
血流が改善されることで、組織への酸素供給が増え、新陳代謝が活発になります。また、老廃物や二酸化炭素の排出が促進されるため、炎症の軽減や疲労回復が期待できます。このメカニズムは、鍼治療が慢性疲労やスポーツ後のリカバリーに効果的である理由の一つです。
5. 局所的および全身的な効果
鍼は特定のツボや部位への刺激により局所的な血流を高めると同時に、全身の循環系にも影響を及ぼすことができます。例えば、膝や肩などの局所的な痛みに対して鍼を使用すると、その部位の血流が改善され、痛みが軽減されます。一方で、全身のツボ(例:足三里や合谷)を刺激することで、全身の血液循環が改善されるとも言われています。
6. 冷え性や末端循環障害の改善
特に冷え性のような末端循環障害において、鍼治療は有効です。血流が悪いと冷えやしびれの原因になりますが、鍼は末端の毛細血管の血流を促進し、手足の温まりやしびれの緩和に寄与します。
7. 科学的な研究とエビデンス
現代の研究において、鍼治療が血流を改善するメカニズムが徐々に明らかになってきています。例えば、赤外線サーモグラフィーを使用した研究では、鍼治療後に皮膚温度が上昇することが観察されており、血流の改善が裏付けられています。また、超音波やMRIを用いた調査でも、特定のツボへの鍼刺激が血流速度を向上させることが示されています。